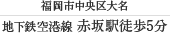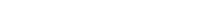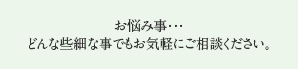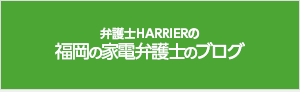本日、いわゆる「退職代行」運営会社と、これと提携しているとされる法律事務所に、弁護士法違反(周旋)の疑いで、警視庁による家宅捜索が行われた旨の報道がありました。
ここで「周旋の疑い」とされているのは、具体的には、本件「退職代行」運営会社が、勤務先からの退職を希望する人から勤務先会社との交渉を、弁護士に取次ぎ(周旋=紹介)、その対価として弁護士から報酬を受け取っていた疑いがある、というものです。
本件がどういう展開を見せるかはこれからの捜査を見守るしかありませんが、ここで皆さんに知っておいていただきたいのは、「どうして、弁護士との間で顧客紹介の対価を支払うことが禁じられているのか」です。
1 形式的理由
顧客を「周旋=紹介」して、その対価として弁護士との間で報酬を授受することは、一般的に
・報酬をもらった(紹介した)側の業者=弁護士法72条
・報酬を払った(紹介を受けた)側の弁護士=弁護士法27条(なお弁護士職務基本規定11条)
で禁止されています。
弁護士法違反は、刑罰の対象になりますから、犯罪です。
しかしながら、顧客の紹介があれば、対価の授受をしたいのが人情だと思います。
にもかかわらず、どうして法律(と弁護士職務基本規定)はこれを禁じているのでしょうか?
2 実質的理由
①弁護士選択の自由を事実上奪われる(顧客の不利益)
業者から弁護士が紹介される場合、依頼者にとってベストな弁護士が紹介されるべきところ、紹介料を弁護士から徴収していると、「紹介料を(高く)払う弁護士」に事件を流しがちになります。本来であればより良い弁護士につながるべきところを、紹介料でつながる人を優先しがちになります。
②弁護士に対する搾取・経済的支配につながる(弁護士の不利益ーひいては顧客の不利益)
弁護士が顧客紹介料を支払って顧客誘引を図ることが常態化すると、
・当該支払先を「上流」として顧客獲得を依存しがちになる
・すると「上流」側の業者の立場が強くなり、本来、顧客第一で動かなければならない弁護士の業務において、それが破られる可能性がありえる
・弁護士は、顧客獲得を中間業者に依存するようになり、中間業者に様々な名目(広告料、人材派遣料など)でお金を吸い上げられる端緒となる。
近年、いわゆる「国際ロマンス詐欺救済弁護士」が相次いで摘発されていますが、こうした類型の事件は、簡単に救済できるものではありません。にもかかわらず、これら広告は、依頼すれば救済されるかのような期待を強く抱かしめるページ構成をとっており、顧客に錯誤を生ぜしめるようになっています。こうした広告手法は、弁護士独自で考えるというより、業者が画を描いて、弁護士を集客マシンとして広告を出させて集客し、様々な名目(顧客紹介料、広告料など)で弁護士からカネを収奪するというスキームであることが多いです。
実際、そうした事務所が破綻すると、たくさんのお金を集めたはずなのに、そのお金は弁護士のところにほとんど残っておらず、業者に何らかの形で払い出されているのです。
「紹介料」は、弁護士を「集金マシン」としてカネを収奪するシステムの歯車として機能するという経験則があります。
③業者が顧客獲得に血道を上げがちになる(顧客の不利益)
一般の人から見て、士業が「できる」「やれる」「勝てる」というと、依頼へのインセンティブが高まります。
他方、中間業者は、事件の筋などどうでもよいから顧客を獲得し弁護士に紹介することに強いインセンティブが発生します。紹介料が介在すると、そのことに拍車がかかります。
その結果、無理な案件をそうと説明せずに弁護士に紹介することが横行しがちとなります。
紹介料の授受をしていたら犯罪
法律問題を抱えている方を無償で弁護士に紹介していただくことは、まったく問題ありません。
しかし、紹介に伴ってその対価を受け取ることは、誰から受け取ってもダメです。
もちろん、弁護士も対価を支払うことはできません。
もし紹介の対価の授受があると、それは犯罪ですから、ご注意ください。